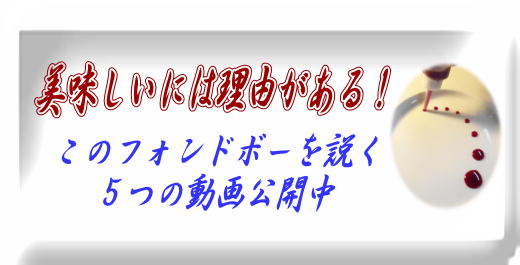海なし県出身者が綴る「江戸前寿司」への憧憬

海と新鮮な魚介類への憧れ、そして江戸前寿司の世界
私の故郷は、関東地方の北部、豊かな緑に囲まれた群馬県です。海に囲まれた島国である日本にありながら、群馬県には海がありません。
幼い頃から、広大な海の景色や新鮮な魚介類への憧れを募らせていました。友人との遠出が叶う年齢になると、旅先に選んだのは決まって海辺の街でした。
新潟県や神奈川県の海岸線に並ぶ、新鮮な魚介類がたっぷりと乗った海鮮丼のお店を見るたびに、その憧れは一層強くなっていったことを覚えています。
私と同じように、遠い昔、100年以上前の江戸に生きた人々もまた、新鮮な魚介類を強く求めていたそうです。
当時の冷蔵技術は未発達で、海から内陸へと魚介類を運ぶ間に、それらは腐敗し、食することは困難でした。
そんな時代に誕生したのが、「漬ける」という画期的な保存方法でした。
特に、マグロを醤油に漬け込むことで空気に触れるのを防ぎ、鮮度を保てるという発見は、まさに食文化における革新だったのです。
江戸前寿司の誕生と進化:海の恵みを内陸へ
この「漬ける」という技術は、後に江戸前寿司の基盤となりました。江戸前寿司は、単なる保存食ではありません。
限られた条件下で、いかに魚の美味しさを最大限に引き出すかという工夫から生まれた、日本の食文化の結晶なのです。
当時の江戸湾で獲れる魚介類(「江戸前」とは江戸湾で獲れるものを指す言葉でもあります)を使い、
米と組み合わせることで、新鮮さを保ちながら美味しく食べられる料理として発展しました。
現代では冷蔵技術が飛躍的に進歩し、東京をはじめとする日本の内陸部でも、とれたての魚のような新鮮な寿司を味わえるようになりました。
私の故郷である群馬県にも、今では多くのお寿司屋さんが軒を連ねています。
それでも、私の中には幼い頃から抱いていた海への憧れと、新鮮な魚介類を求める気持ちが深く残っています。
だからこそ、お寿司屋さんを訪れるたびに、特別な喜びを感じるのです。
江戸前寿司の歴史をさらに深掘りすると、冷蔵技術がなかった時代の人々の知恵と工夫に驚かされます。
魚介類を美味しく安全に食べるための様々な試行錯誤が、現代の寿司の形を築き上げてきたのです。
例えば、酢飯もその一つです。酢には殺菌作用があり、ご飯を腐敗から守るだけでなく、魚の臭みを消し、風味を豊かにする効果もあります。
—
海を越えた「寿司」の魅力:海外からの視点
近年、寿司は日本を代表する料理として、世界中で愛されています。
特に欧米諸国では、「寿司 インバウンド」という言葉が生まれるほど、訪日外国人観光客にとって欠かせないグルメとなっています。
しかし、初めて寿司を口にする外国人の方々にとっては、その独特の食感や文化が新鮮な驚きとなるようです。
フランス人寿司初心者の本音:最初の体験
あるフランス人の寿司初心者は、18年間一度も寿司を食べたことがなかったと言います。
なぜ寿司がこれほど人気なのかを知りたいという強い好奇心から、初めて寿司に挑戦しました。
彼にとって、醤油で柔らかくなった魚の食感は「今まで食べたことのない食感」だったそうです。
最初はそれほど感動するほどではなかったものの、子供の頃から様々な食感のアジア料理を食べてきた経験から、最終的には美味しいと感じたと言います。
「確かに怖いかもしれませんね。だって、生のものは何でもちょっと変な感じがするんです。
まずはカリフォルニアロールみたいに自信のあるものから始めて、だんだん冒険していきましょう。
すぐにみんなと一緒に刺身を食べられるようになるはずですよ!」
この言葉は、寿司初心者の方々が抱く不安を率直に表しています。生魚への抵抗感は、特に欧米文化圏の方々にとっては自然な感情かもしれません。
しかし、一歩ずつ慣れていくことで、やがて生魚の美味しさにも目覚めることができるという、温かい励ましの言葉でもあります。
スウェーデン人から見た寿司:食文化の背景
また、あるスウェーデン人の方は、出身地や住んでいる場所によって寿司の印象は多少異なると語っています。
スウェーデンでは、生の魚(マリネや塩漬け)が伝統的な食文化の重要な一部を占めているため、
初めて寿司を食べた時も、「ああ、こういう風にできるんだ」という自然な感覚だったそうです。
スウェーデンで安価な寿司を食べることについても、特に問題はないと述べています。
安価な魚はそれなりの質ではあるものの、食べられないということはなく、ただ、個人の好みとしては甘すぎることが多いと感じるようです。
これは、地元の魚のマリネの仕方に起因するのかもしれません。
現在、ドイツ中部に住んでいるこのスウェーデン人の方は、安価な寿司の質には不満があると言いますが、
ハンブルク(沿岸部)やポーランド(塩漬けニシンが最高の国)では、安価な寿司でも良い経験をしたと語っています。
このことから、地域やその地の食文化によって、寿司の質や味わいの基準が異なることがうかがえます。
「そうですね、場所や食文化によって多少は違うと思います。
いずれにせよ、気に入ったものがあれば、どこに行っても試してみると思います。食べ物は高価である必要はありません。」
この言葉は、食に対する柔軟な姿勢を示しています。
高価であるかどうかに関わらず、自分の「美味しい」と感じるものを大切にするという考え方は、食を楽しむ上で非常に重要です。
初めての寿司体験:友人との出会い
別の体験談では、友人と地元の鉄板焼きレストランで初めて寿司を食べた時のことが語られています。
今まで寿司を食べたことがないと言うと、友人が注文していた寿司を分けてくれたそうです。
「変な食感」という感想を漏らすと、友人は笑いながら「あの食感は慣れるものだよ」と冗談を言ったと言います。
このエピソードは、初めての体験における戸惑いと、それを温かく受け入れる友人との関係性を感じさせます。
安価な寿司と「慣れる」こと
興味深いのは、初めて寿司を食べる人に「どうやって食べるの?」と聞く前に、「安い寿司は食べないで」と答える人が非常に多かったという声です。
この方は、大学で提供された寿司、つまりスーパーで売られているのと同じブランドの寿司を食べることで、寿司に慣れていったそうです。
この経験は、「高価な寿司でなければ美味しくない」という先入観を打ち破り、日常的に触れる機会から寿司の魅力に気づくこともあるという示唆を与えてくれます。
寿司初心者に向けたアドバイス
「まずは、調理済みの具材を使った巻き寿司、カニやエビ、ウナギなどから始めることをお勧めします。
それから、調理済みのエビを乗せた握り寿司に挑戦してみてはいかがでしょうか。
それから、サーモンやマグロなどの生の食材にも挑戦してみてください。ただし、いきなり生の食材に飛びつくのは絶対に避けてください。
今では生のマグロが大好きですが、最初はそうではありませんでした。カニが一番好きで、一番食べやすいのもカニだと思います。」
この具体的なアドバイスは、寿司初心者が無理なく寿司の世界に足を踏み入れるための、非常に実践的な手引きとなります。
段階的に「生」の食材に慣れていくことで、抵抗感を減らし、最終的には多様な寿司の魅力を存分に楽しめるようになるでしょう。
—
江戸前寿司のさらなる魅力と奥深さ
江戸前寿司は、単に新鮮な魚と酢飯を組み合わせた料理ではありません。
そこには、長い歴史の中で培われてきた職人の技と、日本の美意識が凝縮されています。
例えば、シャリ(酢飯)の温度や握り加減、ネタとシャリのバランス、そして「つけ場」と呼ばれる職人の調理場での所作に至るまで、すべてが計算し尽くされています。
現代の寿司は、冷蔵技術の発達により、世界中の様々な魚介類をネタとして使用できるようになりました。
しかし、江戸前寿司の原点には、江戸前の海の恵みを最大限に活かすという思想があります。
旬の魚を見極め、それぞれの魚に合った下処理を施し、最も美味しい状態で提供する。
この職人のこだわりこそが、江戸前寿司の真髄なのです。
「江戸前寿司」と「早川 光」:知の探求へ
江戸前寿司について深く知りたい方には、早川 光氏の著書『日本一江戸前鮨がわかる本』を心からお勧めいたします。
|
|
この書籍は、江戸前寿司の歴史、文化、そして職人の技術までを網羅した一冊であり、読者レビューの評価も非常に高く、多くの方に支持されています。
寿司に関する知識を深めたい方、寿司の奥深さに触れてみたい方にとって、まさに必携の一冊と言えるでしょう。
この本を読むことで、一口の寿司に込められた職人の心意気や、日本の食文化の奥行きを感じることができるはずです。
海外からの視点も交えながら、寿司が持つ多様な魅力に触れてきました。
私の海への憧れから始まった寿司への思いは、今や世界中の人々の好奇心や感動とつながっています。
食は文化であり、歴史であり、そして人々の心を豊かにするものです。
寿司が、これからも多くの人々に喜びと感動を与え続けることを願っています。
だし巻き卵のはんなりな江戸前ギョク(握り寿司)
by 嵯峨 恭也

材料(1人分)
雑穀ご飯 / 1膳弱
だし巻き卵(甘くない、出汁の利いたもの) / 1cm厚さ3枚
板海苔 / 1/4枚
スナップえんどう / 2~3莢
(A)すりごま / 小さじ1/2
(A)柚子皮 / 少々
(A)塩麹 / ひとつまみ
すし酢 / 大さじ1
レシピを考えた人のコメント
一般的なギョク(卵の握り)は甘い卵が使われていますが、ふんわりしただし巻き卵を使って、ボリューム満点に仕上げました。スナップえんどうの食感がアクセント。